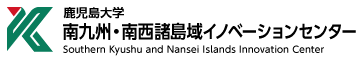3.南九州・南西諸島域ラウンドテーブル
|
当センターでは,地域の課題解決に向けヒアリングや調査を実施し,研究シーズとのマッチングを行っている。しかし,その中には学内の研究シーズでは対応できない課題や課題自体を明確に示すことができないという課題も存在する。「南九州・南西諸島域ラウンドテーブル」は,このような地域課題に対して,研究者を含む関係者全員で地域課題を理解し,その解決手法を全員で検討することで,地域課題から生まれるイノベーションを発掘することを目的としたイベントである。 |
|
■第1回 奄美大島における黒糖焼酎粕の利活用について 【主 催】南九州・南西諸島域イノベーションセンター 【開催日】2025 年 2 月 20 日(木)~ 21 日(金) 【場 所】奄美群島大島紬会館会議室 ,㈱奄美大島開運酒造 ,( 有)富田酒造場 【参加者】鹿児島県酒造組合奄美支部,㈱奄美大島開運酒造(2 名),町田酒造㈱(2 名),西平酒造㈱,奄美大島酒造㈱,(有)山田酒造(6 名 ),農学部 教授 藤田 清貴 ,南九州・南西諸島域イノベーションセンター 特任専門員 瀬戸口 眞治 【概 要】 奄美群島では黒糖焼酎が製造されており,その製造過程で発生する黒糖焼酎粕は,基本的に特殊肥料として畑への散布が行われている。農業の盛んな徳之島や沖永良部では農業利用が進んでいるが,黒糖焼酎粕の発生量が最も多い奄美大島では,散布できる畑地が少なく,黒糖焼酎粕の処理に窮している状況である。これまでも黒糖焼酎粕の処理法についてはいくつか提案され,設置した装置もあるが,ランニングコストが高いなどの理由から稼働されていない。今後,実用的な処理法や有効利用法の開発が急務となっている。このような背景から,実用的な黒糖焼酎粕の処理方法の取組について鹿児島県酒造組合奄美支部から本学へ協力依頼があった。 そこで地元焼酎メーカーと本学研究者が直接意見交換し,共同研究の可能性を探ることを目的に,「南九州・南西諸島域ラウンドテーブル」を奄美市で開催した。講師はサトウキビ由来のメラノイジン(抗酸化成分)の有効利用について取り組んでいる農学部 藤田清貴 教授を招聘した。 当日は,藤田教授が「黒糖焼酎粕の健康食品としての可能性」についてを講演し,その後,黒糖焼酎粕の発生状況,現状の処理方法,これまでの取組などについて情報を共有し,黒糖焼酎粕の処理法や有効活用について議論した。その結果,有効活用については藤田教授と食材化を検討していくこととし,実用的な処理法については,工学部の教員等,適切な研究者を模索することになった。 |
 の視察-300x225.jpg) の視察-300x225.jpg) |